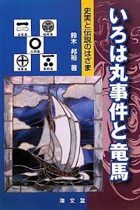
第1章 序
第2章 ワイル・ウエフ号の遭難
第3章 海援隊
第4章 伊呂波丸事件と文献の評価
第5章 伊呂波丸事件における主要事実の認定
第6章 事実の経過
第7章 争点の指摘
第8章 史実と『竜馬がゆく』の矛盾
第9章 事実認定の試み、両船の運動からみた衝突状況
第10章 過失の軽重
伊呂波丸事件についての結論
補説1〜11(水主のこと・海上信仰 観世音菩薩・船長の由来・海里とは・速力のこと・針路のこと・衝突針路・英国艦長の高柳明光丸船将に対する回答全文・ブルック海尉の日記・海図上での距離測定・旧暦グレゴリオ暦対照表
[目次から太字表記部分を引用]
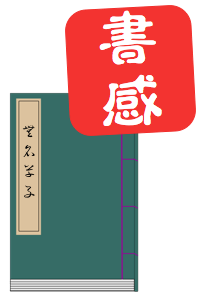 発行が平成二二年(2010年)の末ということもあり、同年四月下旬おおやけにされた新史料(イロハ丸の売買契約書)について、なにかくわしい紹介があるだろうと予測して購入。くわえて著者の鈴木氏は
発行が平成二二年(2010年)の末ということもあり、同年四月下旬おおやけにされた新史料(イロハ丸の売買契約書)について、なにかくわしい紹介があるだろうと予測して購入。くわえて著者の鈴木氏は海難事故調査、海難審判の補佐人
という海事のプロであるらしく、イロハ丸事件の針路問題(イロハ丸が事故のさいとっていた針路には二つの説が存在する)について、専門家らしい判断や解釈があるかとも期待したところ、内容はそれ以前で問題がおおい。
いちいち難をあげていてもキリがないので、大掴みしたに例を数個だけあげるが、この手の手抜かりや問題は、本文の数ページごとに頻出するため、読んでいてヒドく気疲れがする。
たとえば、
- 坂本龍馬に関する知識が基本的に不十分。
- 『英将秘訣』を龍馬語録としてあつかっている。
- 近藤長次郎を海援隊士として紹介する一方、池内蔵太や黒木小太郎を非海援隊士としてあつかっている。
- お龍の別名に「鞆」があることを知らない。
- 当時の文章表現や一般常識にたいするこまかな認識・知識不足が目につく。
- 通称と字(あざな)を混同している。
- 人名に対する当て字を単純に無知ゆえとして批判している。
- 「円」とドルの同義関係を把握していない。
- 歴史性や時系列を無視した批判が多い。
- 現代水準をもとに、幕末期の技術や交渉過程を拙悪として単純に非難する。
- 先行資料や先行著作にみえる不備や間違いを、当時世に出ていなかった後出資料や見解でもって非難する。
- 小説『竜馬がゆく』の創作(フィクション)部分にまで、
衆愚をミスリード
するものとして批判をくわえている。
- 史料批判や資料の選択が何かおかしい。
- 土佐藩側の史料にたいしては特に論証手続きをふまないまま改竄の可能性を指摘する一方で、紀伊藩側の史料にはほぼ無批判で肯定の姿勢を貫いている。
- 土佐藩側の主張には『維新土佐勤王史』のみを資料として活用しており、『坂本龍馬関係文書』や『坂本龍馬全集』など、基本となるその他諸史料を使用していない。
- 龍馬書簡に目をシッカリ通していないとおぼしく、見当違いな指摘が目につく。
などなどである。
なかには自己の知識不足に気づかないまま、他者を逆に批判しているような例(上記では平尾道雄『坂本龍馬海援隊始末』にたいし、
竜馬の妻女鞆子と書いているが、通説によれば妻女の名は「お龍」(おりょう)、旧姓楢崎龍だろうに
と批判するような類い)まであって、観ていて些か痛々しい。
結局、当事件にたいする鈴木氏の裁定は、通説のとおり非はイロハ丸側にあるというもので、その点本書に新味は特段見当たらない。一往、海事のプロがおこなった見解であるというセールスポイントも、
山田一郎『海援隊遺文』など先行例がすでにあるだけ二番煎じの観がある。全体的に同人レベルと評さざるを得ない。
![]() 雑感・感想
雑感・感想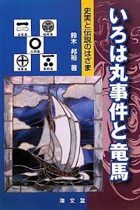 第1章 序
第1章 序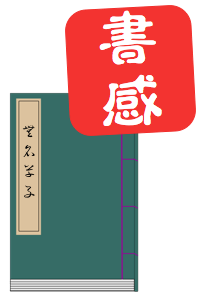 発行が平成二二年(2010年)の末ということもあり、同年四月下旬おおやけにされた新史料(イロハ丸の売買契約書)について、なにかくわしい紹介があるだろうと予測して購入。くわえて著者の鈴木氏は
発行が平成二二年(2010年)の末ということもあり、同年四月下旬おおやけにされた新史料(イロハ丸の売買契約書)について、なにかくわしい紹介があるだろうと予測して購入。くわえて著者の鈴木氏は