天保六年〜安政五年
龍馬の剣術の腕について最近では色々な説を耳にする。ある人は龍馬を「達人」と観、またある人は「イメージ先行の凡人」と観る。
龍馬は十四歳から小栗流の修行を開始するわけだが、この修行開始「年齢的にあきらかに遅い」とする説を聞いたことがある。試しに同時代人の修行開始年齢を思いつくまま記してみると下記のようになった。
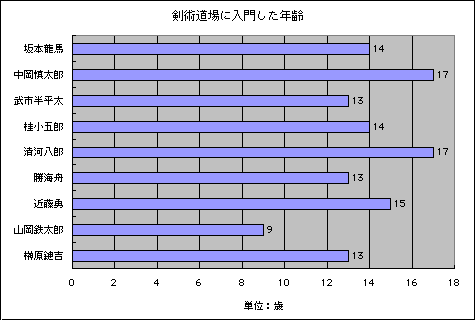
(異説がある人物もいるので注意)
上記の例を見るかぎり、龍馬の入門ははやいわけでもないが別段遅すぎるわけでもなさそうだ。
ではつぎに日根野道場の実力を推しはかる材料として、龍馬と同門の主な勤王党系の人物を見てみると
●「馬に過ぐる」とも称される健脚と人並みハズれた膂力が伝えられる偉丈夫。岩崎甚左衛門・那須俊平らより鑓術免許を、日根野弁治より小栗流の免許を授かったと伝わる。天誅組では軍監をつとめた吉田東洋暗殺者の一人 那須信吾。
●長谷川流居合術の達人 高松順蔵を父にもち、九州へ武者修行にも出た経験のある龍馬の甥 高松太郎。彼はのちに武市半平太が勅使護衛のため、腕ききを選んだ随行員の一員にも選ばれている。
●五十人組の一員として上府し、小田原で郡の剣術取立役坂本瀬平殺害にも関与した檜垣清治。一説には武市道場の塾頭をつとめたともいう。
●禁門の変で那須俊平と共に奮戦し、土州兵一番鑓をあげた尾崎幸之進。
●父の前田常五郎に武術を習い、剣を日根野弁治、鑓を岩崎長武に学んだ。のち自ら武術教授の道場を開いたという三条実美の衛士 前田要蔵。
上記のような人々が、とりあえず思い浮かぶ。この中にあって定員十二名の小栗流皆伝免許を授かり、師の代理をつとめたという龍馬の腕が「イメージ先行の凡人」だったとは思えない。
また龍馬が入門したころ、その師範代をつとめた土居楠五郎と龍馬の皆伝までの速度を比較してみる。
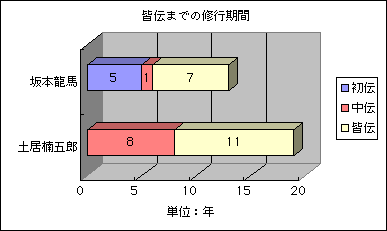
土居楠五郎が初伝を授かった時期は不明ながら、皆伝までわずか十三年を要したに過ぎない龍馬の非凡さが目につく。これで小栗流および土佐藩における龍馬の力量を知ることができると思うが如何であろう?
ついでに藩内における比較としてもう一つ。小野派一刀流を修行し、その免許皆伝を授かった武市半平太との比較も以下に行ってみよう。
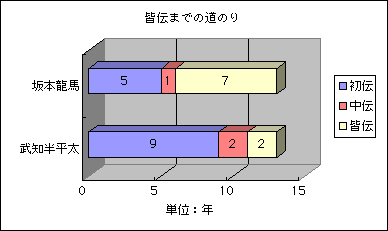
(武市の入門年齢には諸説があるが、ここでは十三歳を基準に作成)
土佐藩を代表する使い手として知られ、のちに鏡新明智流士学館の塾監をつとめた武市と比べてみても、龍馬のはやさに遜色は見られない。
なお龍馬の場合、十三年間のうち都合三年間は江戸で北辰一刀流の修行に励んでいたことも付記せねばなるまい。
(平成某年某月某日識/平成一八年二月二〇日訂)