天保六年〜安政五年
![]() 龍馬の技量
龍馬の技量
剣術や鑓術など、武術における個人々々の実力を、正当に評価するのは難しい。世に「剣客」・「剣豪」として知られる人物でさえ史料によった考証から、その実力に疑問符がつけられる例など決して珍しくは無いだろう。それは剣豪の代名詞ともいえる宮本武蔵に対して「非名人説」をとなえる人がいるように極めて自然なことである。
龍馬の実力に対し疑問符をなげかける場合、「北辰一刀流長刀兵法目録」を根拠にあげ「龍馬は剣術ではなく薙刀の目録しか伝授されていないではないか」と論じられる。なるほど、確かに一応はごもっともな説である。しかし北辰一刀流は兎も角として「小栗流」における龍馬の実力は世に「一流」として称される剣客剣豪たちと比較しても決して見劣りするものでは無い(詳しくは別稿参照)。
付言するならば、小栗流において他を圧するほどの非凡さを見せる龍馬が北辰一刀流で薙刀の目録しか伝授されていないと考えるのは、さすがに面妖というほかないだろう。龍馬の遺品・家信の類は高松太郎から子の坂本直衛へと相続されたが、この直衛には遺品若干を他に売り払った形跡があり、大正二年におきた釧路大火でも遺品・家信の類はいくつか燃えている。さらに盗難にあったもの、何らかの事情で坂本家に伝わらなかったものなどを考えあわせてみると龍馬の北辰一刀流剣術伝書は現存していないのか、まだ発見されていないと見るのが妥当なように思われる。そもそも幕末の有名な剣客の中で、どれだけの人物が現在にその伝書を伝えているというのか。龍馬の場合、小栗流の皆伝「小栗流和兵法三箇条」が現存する以上、薙刀の目録のみを根拠にその実力を論断するのは些か乱暴というほかない。
では剣客の場合、実力を推し量る材料としてよく使われる伝記史料において、龍馬の評価は如何なものか。『汗血千里駒』では以下のように評している。
●『汗血千里駒』
龍馬は神田お玉ヶ池なる千葉周作氏の門に入て、専ら剣道に心を委ね只管勉強なしたるゆえに、後には土州藩士に剣客坂本龍馬其人ありとまで算えられて諸藩を遊歴なすほどに至りける。
詳しくは後述するがこれを的を射ていると評しても、さほど差し支えはあるまい。
別稿でも軽くふれたが千頭清臣『坂本龍馬』によると龍馬は二十歳で小栗流の師範代をつとめたことになっている。流派や地方が異なるため参考にはならないかも知れないが、新選組の沖田総司は十九歳の文久元年頃には師の代稽古をつとめていたという。この場合、龍馬と沖田を比較してみれば、入門期間から考えても理屈上、龍馬の上達速度は沖田のそれ凌ぐことになる。(沖田が道場に入門したのは十二歳の頃で、龍馬は十四歳で入門)
以上から見ても伝記史料における龍馬の評価は極めて高い。では同時代の人々から見た場合はどうか。下にいくつかの評をまとめてみた。
●信太歌之助の評
勝海舟の手紙に坂本は剣術はなかなかつかえる、組打ちも上手だと書いてありました
●谷守部の評
両人[龍馬・中岡慎太郎]共に武辺の場数者、特に坂本は剣術の秀逸なれば、顔を見合して話をしつつヲメヲメ斬らるる恥鈍漢にあらず
●大石鍬次郎の評
かねがね[近藤]勇話には坂本龍馬打取り候者は見廻組今井信郎、高橋某等少数にて、剛勇の龍馬を打留め候儀は感賞致すべし
●住谷寅之介の評
龍馬誠実可也の人物、しかして撃剣家
●吉田健蔵の評
撃剣家坂本氏
●香川敬三の評
剣客、航海学の志あり
●千葉佐那の評
父は坂本さんを塾頭に任じ、翌五年一月には北辰一刀流目録を与えました
他にも口伝として紹介できうる評もあるが上記の中だけでも何種類かの評を散見することができる。この人々から見た場合でも龍馬の剣に対する評価は決して悪いものではない。
この中で面白いのが住谷寅之介・吉田建蔵・香川敬三といった水戸藩出身の三名が龍馬を「撃剣家」・「剣客」と評している点だ。そもそも「武」を生業としている新選組や道場主たちと違って、龍馬にその手が評が少なくなるのは当前のことだろう。しかし、この三名は龍馬を評する事に何故か、異口同音に「剣」について着目している。ことさら「撃剣家」・「剣客」と龍馬を強調する以上、偶然と考えるよりは水戸藩と縁の深い(千葉周作一家は水戸藩から禄を受けている)北辰一刀流における龍馬の名声を評した言とみるのが自然ではなかろうか。少なくとも『汗血千里駒』が評するが如く「土州藩士に剣客坂本龍馬其人ありとまで算へられ」たのは事実とみるのが妥当である。
別稿でふれている「安政御前試合」などの類は後世の人々が「剣客」としても龍馬をみていたことを表す証左であろうが、似たような話に新選組と龍馬が斬り合いになったという話がある。安芸藩講武所助教・丹羽精蔵(玄武館および練兵館門下)の略伝に見られる逸話で元治元年、龍馬と二人で京都堀川沿いを歩いていると新選組六名と遭遇し、二人は立ち所に一名ずつ斬り「これを走ら」せたという。内容自体は眉唾モノだが丹羽精蔵の「略伝」で、わざわざ龍馬を持ち上げる必要性が無いことを考えると、龍馬と同等の活躍を丹羽に演じさせることが何かしら「意味がある」と言うことなのだろう。
評の中で注意して貰いたいのが千葉家と龍馬との関係である。上にも記したように佐那は小千葉道場塾頭の座に龍馬がついていたことを証言している。さらに定吉が公認のもと二人は婚を約したと言うのだから「家」単位で結婚が考えられていた当時、このことは北辰一刀流の道統を継ぐに足る実力が龍馬に備わっていると定吉が判断したからに他あるまい。龍馬が修行した北辰一刀流両道場のうち、定吉が鳥取藩に出仕していた関係上、小千葉道場で実質的に教授に当たっていたのは千葉重太郎だと思われ、一方の玄武館においては周作の没後、千葉栄次郎が道場を支えていた。龍馬はこの二人とも交情が深かったようで重太郎と龍馬は共に同志的行動をしているし、栄次郎に至っても「龍馬と深い交わりを結び、国事に奔走」するようになったと言う。
以上のように塾頭だったと言う証言や婚約、実質的な師二人との交友などを鑑みると龍馬に剣の実力がなかったとは言えないよう思われる。(むしろ実力が無いと考える方が些か無理があるのでは無かろうか)
余談だが北辰一刀流宗家第五世 小西重治郎氏の著書によると龍馬の伝位は「中目録免許」であったらしい。これに従って同門の中でも伝位を授かった時期がハッキリしている選りすぐりの剣客たちと比較してみた。簡単な目安にはなるだろう。
なお龍馬が中目録を授かった時期は判然としないため下図の場合、嘉永六年から安政五年まで(つまり江戸再遊終了まで)の五年間と仮定している。
●龍馬暗殺を評した小西重治郎氏の言(『よみがえる北斗の剣』)
彼[龍馬]は千葉道場で中目録まで進んでいたのだから相当の使い手だった。しかし太刀には長じていたが小太刀をあまりやらなかった。加えての油断であった
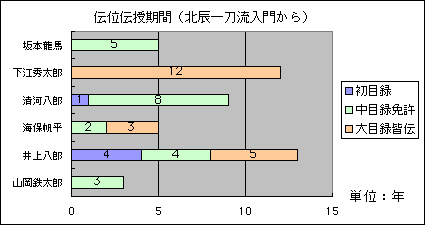
北辰一刀流入門からの伝授期間
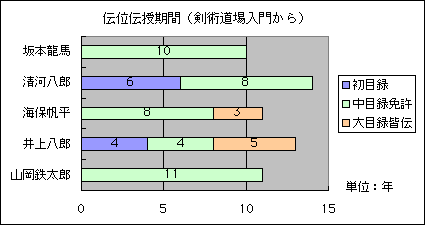
剣術道場入門からの伝授期間
(平成某年某月某日識)